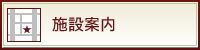ここから本文です。
更新日:2025年8月18日
令和8年度(2026年度)から適用される個人住民税(市県民税)の主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として、次の内容が令和8年度課税(令和7年分所得)から適用となります。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
この改正に伴い、単身者で給与収入のみの人の場合、非課税となる収入額は年間で93万円以下から103万円以下へと10万円引き上げられます。詳しくは『個人住民税の非課税ラインについて』(PDF:146KB)をご覧ください。
配偶者控除および扶養控除適用の所得要件の緩和
配偶者控除および扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得金額48万円から58万円以下に緩和されます。
改正前と改正後の比較
| 区分 | 改正前の所得要件 | 改正後の所得要件 |
|---|---|---|
| 合計所得 | 48万円 | 58万円 |
この改正により給与収入のみの場合、年間の収入が123万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。配偶者や親族等に年金など、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超えているため、扶養控除が適用できない場合であっても、所得額に応じて段階的に控除を受けられる仕組みが創設されます。
個人住民税の特定親族特別控除一覧
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
- 所得税と比べて区分や控除額が異なります。
- 控除額を認めるものであるため、扶養親族には含まれません。
ひとり親控除適用の所得要件の緩和
ひとり親控除を適用するための所得要件が、総所得金額等が48万円以下から58万円以下に緩和されます。
勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得金額75万円以下から85万円以下に緩和されます。
家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
シルバー人材センターの配分金等に適用される家内労働者等の特例の適用について、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
その他(所得税について)
令和7年分以降の所得税において適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ内の『令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部サイトへリンク)をご覧ください。