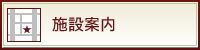ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
赤穂義士略式年表
元禄事件略年表
| 元禄14年 (1701) |
元禄15年 (1702) |
元禄16年 (1703) |
宝永2年 (1705)~ |
正徳3年 (1713) |
延享4年 (1747) |
寛延元年 (1748) |
|---|
元禄14年(1701)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2.4 | 浅野内匠頭長矩に勅使御馳走役、伊達左京亮宗春に院使御馳走役を命ずる |
| 3.11 | 勅使柳原資廉・高野保春、院使清閑寺熈定、伝奏屋敷に到着する。 |
| 3.12 | 勅使・院使登営。将軍綱吉へ勅旨・院旨を伝える |
| 3.13 | 勅使・院使登営。将軍綱吉、饗応能楽を催す |
| 3.14 | 勅使・院使登営。江戸城松の廊下で浅野長矩、吉良上野介義央に刃傷事件起こす。浅野長矩、田村右京大夫建顕へお預けとなり、夕刻切腹、夜泉岳寺に葬られる。事件を報ずる第一の早使、足軽飛脚、第二の早使が赤穂へ向けて発つ |
| 3.15 | 浅野大学長広、閉門を仰せ付けられる。赤穂城受城使に脇坂淡路守安照・木下肥後守公定を任命 |
| 3.17 | 浅野鉄砲洲上屋敷を引き渡す |
| 3.18 | 浅野赤坂下屋敷を引き渡す |
| 3.19 | 第一の早使、続いて浅野長広書状、第二の早使が赤穂へ到着 |
| 3.20 | 赤穂藩札の六歩引換えを始める(3月28日終了) |
| 3.21 | 浅野長広閉門の知らせが赤穂へ到着する |
| 3.26 | 吉良義央、辞職。以後、寄合に列す |
| 3.27~3.29 | 大石内蔵助良雄、藩士を赤穂城中に集め大評定 |
| 3.29 | 大石良雄、受城目付宛の「欝憤之書付」を持たせ多川九左衛門・月岡次右衛門を江戸へ派遣 |
| 4.5 | 多川九左衛門・月岡次右衛門、受城目付に大石良雄の「欝憤之書付」を渡せず、戸田氏定に見せる |
| 4.11 | 大石良雄ら切腹の連判をする(4月12日現在で29人、都合64人)。多川九左衛門・月岡次右衛門、江戸より戸田氏定の書状を持って赤穂へ帰る |
| 4.12 | 大野九郎兵衛一家、赤穂から逃亡する |
| 4.13 | 赤穂城内の武具・馬具を売り払う |
| 4.14 | 家中、浅野家代々の永代供養のため、花岳寺・大蓮寺・高光寺へ田地を寄進 |
| 4.15 | 大石良雄ら、残務整理の会所を城下加里屋の遠林寺に移す。赤穂藩家中、赤穂城下を退去する。大石良雄一家は尾崎村へ移る |
| 4.16 | 受城目付荒木政羽・榊原政殊、赤穂へ到着する |
| 4.17 | 幕府の代官石原正氏・岡田俊陳、赤穂へ到着する |
| 4.18 | 目付・代官の城内見分。赤穂近隣の諸藩、陸海の警戒にあたる |
| 4.19 | 受城使脇坂安照・木下公定、赤穂城を請け取る |
| 5.11 | 受城目付荒木政羽・榊原政殊、赤穂を発ち江戸へ向かう |
| 5.20 | 大石良雄、遠林寺祐海を江戸に派遣、護持院隆光に浅野家再興の運動をする |
| 6.4 | 大石良雄ら、残務整理を終え、遠林寺の会所を引き払う |
| 6.25 | 大石良雄、尾崎村を発ち山科へ向かう |
| 6.28 | 大石良雄、山科西山村(西野山)に隠栖する |
| 8下旬 | 大石良雄、原惣右衛門・潮田又之丞・中村勘助を江戸急進派の鎮撫に派遣する |
| 9.2 | 吉良屋敷を呉服橋内から本所(もと松平登之助屋敷)へ移す幕命が出る |
| 9.18 | このころ、大石良雄、進藤源四郎・大高源五を江戸急進派の鎮撫に派遣する |
| 10.23 | 大石良雄、奥野将監らと京都を発ち江戸に向かう(11月2日到着) |
| 11.4 | 堀部安兵衛ら3人、大石良雄を訪ね予備会談をする |
| 11.10 | 江戸会議。大石良雄ら、仇討ちを仮に明年3月と決める |
| 11.23 | 大石良雄、奥野将監らと江戸を発ち京都へ向かう(12月5日帰着) |
| 12.11 | 吉良義央隠居、義周の家督が許可される |
元禄15年(1702)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 1.14 | 山科・伏見の衆、瑞光院の浅野長矩墓所に参拝し、寺井玄渓宅で会談する。 萱野三平、郷里の摂津国豊島郡萱野村で自害する |
| 1.- | このころ、高田郡兵衛脱落する |
| 2.15 | 山科会議。浅野長広の処分を待ってことを起こすを決議する |
| 2.21 | 吉田忠左衛門・近松勘六、山科会議の決議を同志に伝えるため、京都を発ち江戸へ向かう(3月5日到着) |
| 4.中旬 | 大石良雄、妻子を但馬国城崎郡豊岡の実家石束源五兵衛毎公へ帰らせる |
| 5. | 大高源五(俳名子葉)、『誹諧二ツの竹』を出版する |
| 6.29 | 堀部安兵衛、京都に着き、原惣右衛門・大高源五らと仇討ちの相談をする |
| 7.18 | 浅野長広、広島差し置きを命ぜられ、広島藩桜田向屋敷へ移る |
| 7.28 | 円山会議。大石・原・堀部ら19人、仇討ちを決議する |
| 7.29 | 浅野長広、妻子と共に江戸を発ち広島へ向かう(8月21日到着) |
| 8.10 | 堀部安兵衛・潮田又之丞、江戸に到着する |
| 8.12 | 堀部ら江戸の同志、隅田川舟上会議を開く |
| 8.- | 大石良雄、横川勘平・貝賀弥左衛門・大高源五に同志を訪ねさせ神文判形の返戻をさせる |
| 閏8~10 | このころ、脱盟者相次ぐ。同志は江戸に集結する |
| 9.24 | 大石主税良金ら江戸に到着 |
| 10.7 | 大石良雄ら、京都を発ち武蔵国平間村に向かう |
| 10.26 | 大石良雄ら、平間村へ到着する。平間村滞在中、討入り心得書「覚」を作る |
| 10. | このころ、吉良邸の図面2枚を入手する |
| 11.5 | 大石良雄、平間村を発ち江戸石町に居を移す |
| 11.13 | 大石三平、中嶋五郎作・羽倉斎から得た吉良情報を堀部安兵衛に知らせる |
| 11.29 | 大石良雄、落合与左衛門を通じて瑶泉院に「預置候金銀請払帳」を提出 |
| 12.2 | 深川会議。同志一同、深川八幡前の茶屋に集合し「人々心覚」を決める |
| 12.3 | 大石家来瀬尾孫左衛門・足軽矢野伊助、離脱する |
| 12.5 | 当日の吉良茶会が延期と判明し、討入りを延期する |
| 12.11 | 毛利小平太、離脱する。大石良雄、討入り部署を定める |
| 12.14 | 大石三平・大高源五から吉良茶会の情報が入る。大石良雄、12月15日早朝の討入りと決し、同志を本所の堀部安兵衛宅などへ集結させ武装する |
| 12.15 | 吉良邸討入り事件起こる 赤穂四十七士、吉良邸に討入り、吉良義央を討ち取る。途中、吉田忠左衛門・冨森助右衛門、大目付仙石伯耆守久尚に自訴する。残りの44人、泉岳寺へ引き揚げ、浅野長矩墓前に吉良義央の首級を手向ける |
| 12.16 | 細川越中守網利(熊本藩)へ17人、松平隠岐守定直(伊予松山藩)へ 10人、毛利甲斐守網元(長府藩)10人、水野監物忠之(岡崎藩)へ9人、それぞれお預けとなる |
| 12.23 | 評定所、吉良・上杉方は厳罰、四十六士はお預け差し置きとする「存知寄書付」を老中へ提出する |
元禄16年(1703)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 2.4 | 四十六士、お預け先4藩の江戸屋敷で切腹。吉良義周、知行地を没収され、諏訪安芸守忠虎(諏訪藩)へお預けを命ぜられる。大石らの遺児19人に遠島仰せ付けられる |
| 2.11 | 吉良義周、江戸から諏訪の高島城へ護送される(2月16日到着) |
| 4.28 | 浪士の遺児吉田伝内・間瀬定八・中村忠三郎・村松政右衛門、伊豆大島へ遠島となる |
宝永2年(1705)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 4.27 |
間瀬定八、伊豆大島で病死する |
宝永3年(1706)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 1.20 | 吉良義周、配所の諏訪高島城で死去(2月4日地元の法華寺へ埋葬) |
| 8.12 | 吉田伝内・中村忠三郎・村松政右衛門、遠島赦免となる |
宝永6年(1709)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 7.18 | 浅野長広、広島藩差し置き赦免となる |
| 8.20 | 浅野長広、帰府を仰せ付けられる(10月25日江戸帰着) |
宝永7年(1710)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 9.16 | 浅野長広、安房国に新知500石を与えられ、寄合に列せられる |
正徳3年(1713)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 10.1 | 大石大三郎(良雄三男)、広島藩浅野安芸守吉長に召し抱えとなり広島に到着 |
延享4年(1747)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 10.6 | 寺坂吉右衛門、江戸で死去。麻布曹渓寺に葬られる |
寛延元年(1748)
| 月日 | 出来事 |
|---|---|
| 8.14 | 竹田出雲(二世)・三好松洛・並木千柳の浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」が大坂竹本座で上演される |
参考文献/『赤穂市史』第2巻(昭和58年、赤穂市刊)。『忠臣蔵』第1巻(平成元年、赤穂市刊)
お問い合わせ