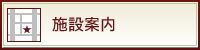ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > ひとり親家庭等への支援 > 母子家庭・父子家庭への支援
ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
母子家庭・父子家庭への支援
母子・父子自立支援員
母子家庭・父子家庭の身上相談に応じるため「母子・父子自立相談員」を配置し、相続、子どもの認知など法律問題の特別相談などについて相談をお受けします。
児童扶養手当
父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
詳細は、市ホームページ児童扶養手当をご覧ください。
母子家庭等医療費助成制度
母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童を対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。
詳しくは、市ホームページ母子家庭等医療費助成制度をご覧ください。
養育費・面会交流
離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト「あなたの支え」
こども家庭庁では、ひとり親家庭の働く・暮らす・育てるを支えるため、暮らしに役立つさまざまな支援の情報を掲載しています。
お問い合わせ