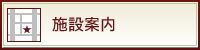ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
海域水質調査結果
目次
海域水質調査結果
古池沖
- 令和6年度調査結果(PDF:48KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
大津川河口
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
江見ノ鼻
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
江見ノ鼻沖
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:48KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
松ノ鼻
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
取揚島
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
千種川河口
- 令和6年度調査結果(PDF:49KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
御崎港
- 令和6年度調査結果(PDF:48KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:24KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
御前岩
- 令和6年度調査結果(PDF:48KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:47KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
放水口地先
- 令和6年度調査結果(PDF:48KB)
- 令和5年度調査結果(PDF:46KB)
- 令和4年度調査結果(PDF:23KB)
- 令和3年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和2年度調査結果(PDF:22KB)
- 令和元年度調査結果(PDF:22KB)
生島沖
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ