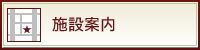ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市県民税)・森林環境税(国税)
ここから本文です。
更新日:2024年4月8日
個人住民税(市県民税)・森林環境税(国税)
納税義務者
個人住民税および森林環境税の納税義務者は、次のとおりです。
|
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|---|---|
|
市内に住所がある人 |
個人住民税均等割額+個人住民税所得割額+森林環境税額 |
|
市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人で、赤穂市内に住所がない人 |
個人住民税均等割額 |
(注意)市内に住所があるかどうか、また事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。例えば、1月2日以降に赤穂市から他市へ転出しても、その年の住民税は赤穂市に納めていただくことになります。
個人住民税および森林環境税が課税されない人
個人住民税均等割・所得割および森林環境税が課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦及びひとり親に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない人 38万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族を有する人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8,000円
個人住民税所得割が課税されない人
前年の総所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族のいずれも有しない人 45万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族を有する人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
個人住民税所得割の税率
|
市民税 |
県民税 |
||
|---|---|---|---|
|
一律6% |
一律4% |
(注意)土地建物等の分離譲渡所得などの場合は別の税率を定めています。
個人住民税均等割および森林環境税の税額
|
市民税 |
県民税 |
森林環境税 |
|---|---|---|
|
3,000円 |
1,800円 |
1,000円 |
(注意)県民税には、県民緑税800円を含みます。
所得の種類
所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いた金額です
所得の金額=収入金額-(必要経費・専従者控除・給与所得控除・公的年金控除など)
|
事業所得 |
販売業、製造業、卸売業、飲食業、建設業、サービス業、医師、税理士、外交員、茶・花などの師匠、大工など農業以外の事業所得 |
|
|---|---|---|
|
農業所得 |
農産物の生産、果樹の栽培、養蚕、家畜の飼育などから生じる所得 |
|
|
不動産所得 |
家賃、貸間代、地代、貸ガレージ、権利権などによる所得 |
|
|
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
|
|
配当所得 |
その年1月~12月に支払われた株式または出資金の配当、余剰金の分配、証券投資信託の収益による分配による所得 |
|
|
給与所得 |
給料、俸給、賃金、歳費、賞与などの収入金額から給与所得控除額を控除したもの |
|
|
雑所得 |
(公的年金) |
厚生年金等の公的年金及び恩給などの収入金額から公的年金控除額を控除した金額 |
|
(その他) |
著述家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、郵便年金、生命保険年金、非営業貸金の利子など他の所得にあてはまらない所得 |
|
|
総合課税の譲渡・一時 |
車両、機械、船舶、著作権、漁業権、特許権など資産の譲渡による所得 |
|
所得金額調整控除
下記に該当する所得割の納税義務者は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%
(※)1,000万円を超える場合は1,000万円
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
所得控除の種類
個人住民税の所得控除額は所得税と異なります。
| 控除の種類 | 控除の要件等 | 控除金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民税 | 所得税 | ||||
| 雑損控除 |
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が災害や盗難、横領等にあい住宅・家財・現金などに損害を受けた場合次のいずれか多い金額
|
左の計算 | 同左 | ||
| 医療費控除 |
あなたに、あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費や治療費がある場合
(支払った医療費の総額-保険等で補てんされた金額)-(総所得金額の5%または10万円のいずれが少ない方の金額) 限度額200万円 |
左の計算 | 同左 | ||
| 医療費控除の特例 |
【セルフメディケーション税制】 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」(外部サイトへリンク)を行っている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために「特定一般用医薬品等購入費」(外部サイトへリンク)を支払った場合 (支払った特定一般用医薬品等購入費-保険等で補てんされた金額)-1万2千円 限度額8万8千円 |
左の計算 | 同左 | ||
| 社会保険料控除 | あなたが、あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている国民健康保険、介護保険と後期高齢者医療保険料(本人及び普通徴収によって支払った保険料)、国民年金、厚生年金、雇用保険等を支払った場合 | 支払った金額 | 支払った金額 | ||
| 小規模企業共済等掛金控除 | あなたが、小規模企業共済法による第一種共済の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った金額 | 支払った金額 | ||
| 生命保険料控除 |
あなたや、保険金などの受取人が、すべてあなたや配偶者その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金、また生命保険契約等のうち年金の給付を目的とするもので一定の要件を満たす個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合 |
別表※1の計算:限度額70,000円 |
所得税分の生命保険料控除計算に基づき算出し、 限度額:新契約40,000円、旧契約50,000円 |
||
| 地震保険料控除 |
1.あなたが、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している、家屋、家具、衣服などが地震や噴火などを原因とする火災、損壊などによる損害が生じた時に、その損失分を補填する保険金または共済金が支払われる地震保険を支払った場合 2.あなたが、以下の条件の長期損害保険(経過措置にある長期損害保険料)契約の保険料を支払った場合
注)上記1.2.の両方に該当する契約(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)については、いずれか一方の保険料のみを控除対象とすることになる。 |
別表※2の計算 |
所得税分の地震保険料控除計算に基づき算出し、限度額は50,000 (ただし経過措置にある長期のみの場合は15,000円) |
||
| 寄附金控除 |
あなたが、次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税4%、市民税6%に相当する額
|
左の計算 | 特定寄付金を支出した場合同左 | ||
| 障害者控除 | あなたや同一生計配偶者および扶養親族1人につき |
その他の障害者26万円 特別障害者30万円 同居特別障害者53万円 |
その他の障害者27万円 特別障害者40万円 同居特別障害者75万円 |
||
| 寡婦控除 |
ひとり親に該当しない人で、次のいずれかに該当する人
|
26万円 | 27万円 | ||
| ひとり親控除 | 現に婚姻してない人や配偶者の生死が不明な人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子があり、かつ、あなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 | 35万円 | ||
| 勤労学生控除 | 学校教育法等で規定する学校の生徒で前年中の合計所得が75万円以下で給与等以外の所得が10万円以下の人 | 26万円 | 27万円 | ||
| 配偶者控除 | 合計所得が48万円以下の配偶者 | 別表※3 | 別表※3 | ||
| 合計所得が48万円以下で1月1日現在70歳以上の配偶者 | 別表※3 | 別表※3 | |||
| 配偶者特別控除 | あなたの前年中の合計所得金額が1000万円以下の場合、配偶者(他の納税義務者扶養親族、事業専従者を除く)の合計所得金額に応じて特別控除があります | 別表※3 | 別表※3 | ||
| 扶養控除 | 合計所得金額が48万円以下の一般の扶養親族 | 33万円 | 38万円 | ||
| 19歳以上23歳未満(1月1日現在) | 45万円 | 63万円 | |||
| 70歳以上(1月1日現在) | 38万円 | 48万円 | |||
| 70歳以上(1月1日現在)で同居の直系尊属 | 45万円 | 58万円 | |||
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はありません | 別表※4 | 別表※4 | ||
生命保険料控除(※1)
| 保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|---|
|
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合(x)、下記のそれぞれにつき
|
12,000円以下 | 支払った全額 |
| 12,001円~32,000円 | (x)×2分の1+6,000円 | |
| 32,001円~56,000円 | (x)×4分の1+14,000円 | |
| 56,001円以上 | 28,000円 | |
|
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合(y)、下記のそれぞれにつき
|
15,000円以下 | 支払った金額 |
| 15,001円~40,000円 | (y)×2分の1+7,500円 | |
| 40,001円~70,000円 | (y)×4分の1+17,500円 | |
| 70,001円以上 | 35,000円 | |
| 新契約と旧契約の両方に加入している場合 | それぞれ上記の計算方法で算出しその限度額が28,000円 | |
地震保険料控除(※2)
| 保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1.地震保険料(X)だけの場合 | 50,000円以下 | (X)×2分の1 |
| 50,001円以上 | 25,000円 | |
| 2.経過措置にある長期損害保険料(Y)だけの場合 | 5,000円以下 | 支払った全額 |
| 5,001円~15,000円 | (Y)×2分の1+2,500円 | |
| 15,001円以上 | 10,000円 | |
| 3.両方ある場合※ |
上記1.及び2.により求めた金額の合計 上限は25,000円 |
|
配偶者控除・配偶者特別控除(※3)
|
控除を受ける納税義務者の合計所得金額 |
控除の種類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||||||
| 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | |||
| 配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 (控除対象配偶者) |
33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 配偶者控除 |
| 老人控除対象配偶者 | 38万円 | 48万円 | 26万円 | 32万円 | 13万円 | 16万円 | ||
| 48万円超~95万円以下 | 33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 配偶者特別控除 | |
| 95万円超~100万円以下 | 33万円 | 36万円 | 22万円 | 24万円 | 11万円 | 12万円 | ||
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | 11万円 | ||
| 105万円超~110万円以下 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 | ||
| 110万円超~115万円以下 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 | ||
| 115万円超~120万円以下 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 | ||
| 120万円超~125万円以下 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 | ||
| 125万円超~130万円以下 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 | ||
| 130万円超~133万円以下 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 | ||
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
基礎控除(※4)
|
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
|---|---|---|
|
2,400万円以下 |
||
|
43万円 |
||
|
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 適用なし | |
税額控除
1.配当控除
- 要件1.→課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
- 税率1.→市民税1.6%県民税1.2%
- 要件2.→課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得
- 税率2.→市民税0.8%県民税0.6%
2.調整控除
国から地方への税源移譲に伴い、住民税が平成19年度から一律10%に変更しました。結果として、住民税が増えている方は所得税が減っているために、全体の税負担は変わりません。しかし、所得税と住民税では基礎控除や配偶者控除等の人的控除の金額で、住民税の控除額が少ないために、住民税の税率が5%から10%に上がった場合その差額分だけ、住民税の負担が大きくなってしまいます。調整控除とは、各々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額し、所得税との調整をする控除です。
令和3年度より合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととなりました。
合計所得金額が2,500万円以下の場合
|
課税所得金額※ |
減額措置 |
|
|---|---|---|
|
200万円以下 |
ア:人的控除の差の合計額 |
ア、イのいずれか小さい額の5%を住民税の所得割から減額 |
|
イ:個人住民税の課税所得金額 |
||
|
200万円超 |
{人的控除差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%を住民税の所得割から減額、ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円を減額 |
|
(注意)課税所得金額とは給料や年金等の所得から諸控除を引いた後の金額です。
住民税と所得税の人的控除の差
|
控除の種類 |
金額 |
配偶者控除における人的控除の差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 |
配偶者の合計所得 金額38万円以下 |
控除を受ける納税義務者の合計所得金額 | ||
| 特別 | 10万円 | 900万円以下 |
900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
||
| 同居特別 | 22万円 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 |
| 特別寡婦 | 5万円 |
配偶者特別控除における人的控除の差 |
||||
| 寡夫控除 | 1万円 | 配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者の合計所得金額 | |||
| 勤労学生控除 | 1万円 | 900万円以下 |
900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
||
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円超~40万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 特定 | 18万円 | 40万円以上~45万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 老人 | 10万円 | |||||
| 同居老親 | 13万円 | |||||
| 基礎控除 | 5万円 | |||||
住民税の納付方法
住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。
普通徴収
事業所得者などの住民税は、市役所から発送される納税通知書により年4回(6月、8月、10月、および翌年の1月)の納期で納付してください。
特別徴収
給与所得者の場合
給与所得者の特別徴収については「個人住民税の特別徴収」のページをご確認ください。
65歳以上の公的年金受給者の場合
65歳以上の公的年金受給者の特別徴収については「公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度が導入されます」のページをご確認ください。
減免
天災その他特別の事情がある人、生活保護法による生活扶助を受けている人などで納付が困難な時には、市税条例に基づき減免が受けられる場合があります。減免を受けようとする人は、納期限前までに減免申請書を提出してください。
お問い合わせ