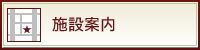ここから本文です。
更新日:2025年3月1日
高齢者住宅改造助成事業について
高齢者・障がいのある人が住み慣れた住宅で安心してすこやかな生活が送れるよう住宅改造費を助成しています。
対象世帯
次の1~3に該当し、生涯にわたり自宅での生活を希望する方が属する世帯
- 介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けた方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方
- 療育手帳の交付を受けた方
内容
- 対象者が日常生活を営むうえで支障となっている部分を取り除くための改造工事が対象となります。
- 1世帯あたりの助成対象限度額は100万円です。ただし、他の制度(介護保険等)から給付が受けられる場合は、それらの制度を優先して利用していただきます。
耐震診断の実施
平成28年4月申請分より、耐震診断の実施が必要となりました。申請の際には、建築年月や過去の耐震診断受診の有無をご確認ください。下記「耐震診断が必要となる住宅」の項目全てに該当する場合は、耐震診断を受けなければ高齢者等住宅改造助成事業の助成を受けることができません。
耐震診断が必要となる住宅
- 昭和56年5月以前に建築された住宅
- 次に掲げる工法に該当しない住宅
- 枠組壁工法
- 丸太組工法
- 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
- 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
- 過去に耐震診断を受けていない住宅
- 延べ面積の半分以上が住宅の用に供されている住宅
簡易耐震診断について
耐震診断を受ける必要がある場合は、都市計画課で実施している簡易耐震診断推進事業を活用できます。「簡易耐震診断推進事業」の利用者負担金を世帯階層区分に応じて、高齢者等住宅改造助成事業で助成します(対象改造工事費と併せて助成上限額は100万円)。
所得制限及び助成率
- 生計中心者に所得制限を超える収入・所得がある場合は、住宅改造助成制度を利用することができません。(介護保険の住宅改修は利用可)
- 「生計中心者」とは、同一世帯の中で最も収入の多い人を指します。また、住民票上は別世帯でも実質的に生計が同じであれば、同一世帯とみなされます。
- 助成率は、世帯(生計中心者)の課税状況で判断します。
| 世帯階層区分 | 住宅改造助成率 |
簡易耐震診断助成額 |
|
|---|---|---|---|
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 3分の3 |
木造:3,150円 非木造:6,350円 |
| B | 生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯 | 10分の9 |
木造:3,000円 非木造:6,000円 |
| C | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 |
木造:3,000円 非木造:6,000円 |
| D | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割課税の世帯 | 3分の2 |
木造:2,000円 非木造:4,000円 |
| E | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円以下の者)で
|
2分の1 |
木造:2,000円 非木造:4,000円 |
| F | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円を超える者)で
|
3分の1 |
木造1,000円 非木造:2,000円 |
注意事項
- 助成を受けるには、事前の手続きが必要です。工事を計画される場合は、必ずご相談ください。工事の着工許可連絡前に工事を開始している場合は助成の対象になりません。
- 予算の関係上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。
- 平成25年4月より受領委任払いでの支払いが可能となりました。
詳細については、下記までご相談ください。
お問い合わせ