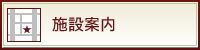ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > ふるさと納税による寄附金控除
ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
ふるさと納税による寄附金控除
ふるさと納税による寄附金控除の概要
自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、以下の表のとおり所得税と個人住民税(市民税・県民税)から控除されます。
| 寄附金控除の種類 | 控除方法 | 控除額の計算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1)所得税寄附金控除 | 所得控除 |
(寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 |
寄附金額の上限は総所得金額等の40%まで |
| (2)個人住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×10% | 寄附金額の上限は総所得金額等の30%まで |
| (3)個人住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) | 控除額の上限は個人住民税所得割額の20%まで |
所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、分離課税に係る税率で計算します。なお、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。
(注意1)(3)個人住民税特例控除における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた税率であり、(1)所得税寄附金控除の税率と異なる場合があります。
(注意2)個人住民税所得割額は、個人住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。
(注意3)ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が個人住民税から控除されます。
ふるさと納税の上限額を求める計算式
ふるさと納税の上限額は、以下の式により算出できます。あくまでも(3)個人住民税特例控除に対する上限を算出する式になりますので、ご留意ください。
上限額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000
所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に分かれているため、この計算式は課税所得金額の階層ごとに以下の表の計算式に置き換えることができます。
また、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額(所得税と個人住民税の人的控除額の差)を差し引いた額で見た税率を使用するため、所得税の課税所得金額と一致しない場合があります。人的控除額の差については、「所得・所得控除・税額控除」のページをご確認ください。
| 課税所得金額-人的控除差調整額 | 所得税の税率 | 上限額を求める計算式 |
|---|---|---|
|
0円以上195万円以下 |
5% |
個人住民税所得割額×23.558%+2,000 |
|
195万円を超え330万円以下 |
10% |
個人住民税所得割額×25.065%+2,000 |
|
330万円を超え695万円以下 |
20% |
個人住民税所得割額×28.743%+2,000 |
|
695万円を超え900万円以下 |
23% |
個人住民税所得割額×30.067%+2,000 |
|
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
個人住民税所得割額×35.519%+2,000 |
|
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
個人住民税所得割額×40.683%+2,000 |
|
4,000万円超 |
45% |
個人住民税所得割額×45.397%+2,000 |
| 所得税の所得区分 | 所得税の税率 | 上限額を求める計算式 |
|---|---|---|
|
上場株式等に係る配当所得 |
15% |
個人住民税所得割額×26.779%+2,000 |
|
株式等に係る譲渡所得 |
||
|
先物取引に係る雑所得等 |
||
|
土地、建物等に係る長期譲渡所得 |
||
|
土地、建物等に係る短期譲渡所得 |
30% |
個人住民税所得割額×33.687%+2,000 |
|
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
40% |
個人住民税所得割額×40.683%+2,000 |
(注意1)個人住民税所得割額は、個人住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。
(注意2)寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅ローン控除などの税額控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
ふるさと納税の上限額の試算
ふるさと納税は、当該年中の収入が確定する前に寄附するものであり、正確な上限額を算定することはできません。そのため、上限額の試算は、下記のいずれかの方法によりご自身で行っていただくようお願いします。
総務省のポータルサイトでの確認
「総務省:ふるさと納税のしくみ(外部サイトへリンク)」より、今年の見込み収入と扶養家族の構成でおおよその上限額を確認することができます。
(注意1)掲載されている早見表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
(注意2)社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
試算シートの活用
赤穂市からお送りしている「市県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」もしくは「市県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」に記載のある内容を基に以下のシートで試算できます。
| お持ちの通知書 | 試算シート |
|---|---|
|
市県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) |
|
| 市県民税・森林環境税税額決定・納税通知書 |
(注意)「市県民税・森林環境税税額変更・納税通知書」では試算いただけませんので、ご了承ください。
ふるさと納税サイトの上限額シミュレーションの利用
年収と家族構成等で計算できる簡易シミュレーションや、各種所得・控除を入力して計算する詳細シミュレーションなどがあります。詳しくは、各ふるさと納税サイトをご確認ください。
控除を受けるには
寄附金控除を受けるには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告が不要になります。(ふるさと納税ワンストップ特例)
確定申告を行った場合、所得税と個人住民税からの控除を受けることになりますが、ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額として控除を受けることになります。
ワンストップ特例制度についての注意点
確定申告や個人住民税の申告を行う等の条件に該当した場合、「ワンストップ特例」は無効になります。詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例が非該当となった方へ」のページをご確認ください。
お問い合わせ